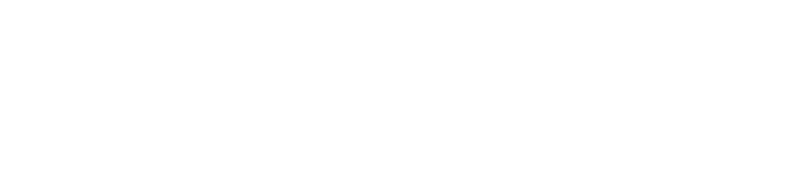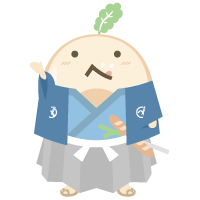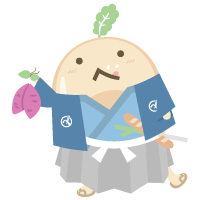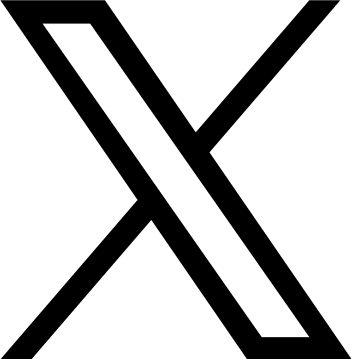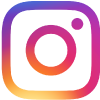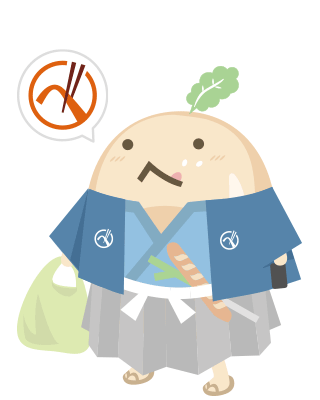「食品ロス」と「フードロス」、何かちがうの?
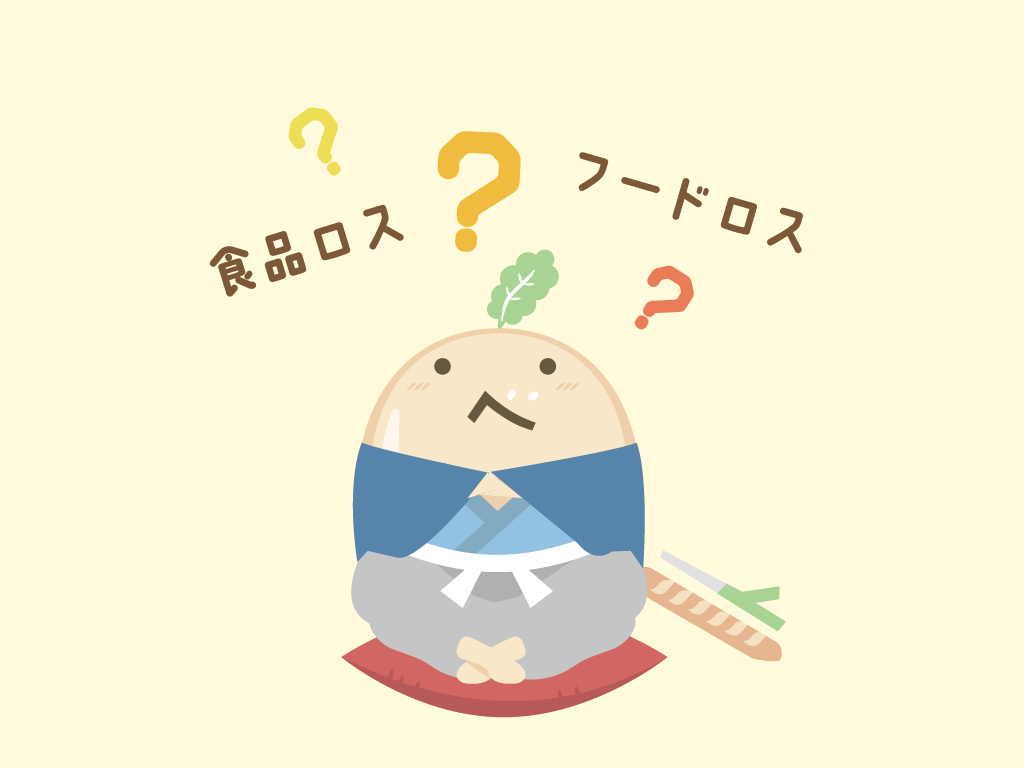
最近よく聞く「もったいない」問題
最近、テレビや新聞などのニュースメディアやスーパーの一画などでも「食品ロス」や「フードロス」という言葉を耳にしたり目にする機会が増えました。どちらも「食べ物のもったいない問題」を指す言葉として使われていますが、この二つ、厳密には少し意味があることを知っていますか?
「食品ロス」とは?
まず、「フードシェアリングサービス タベスケ」で主に使っている「食品ロス」という言葉について。
これは、日本の農林水産省や消費者庁などが使っている言葉で、「本来はまだ食べられるのに、捨てられてしまう食品」を指します。
具体的には、「お店での売れ残り(消費期限・賞味期限切れ間近なもの)」、「見た目が悪いなどの理由で規格外となった食品」、「飲食店での食べ残し」、「家庭での買いすぎ、作りすぎによる廃棄」などが挙げられ、「食べられる部分」が廃棄されることを、特に「食品ロス」と呼んでいます。
「フードロス」との違いは?
一方、「フードロス(Food Loss)」という言葉は、国際的にも使われていますが、より広い意味を持つことが多いです。
海外(国連食糧農業機関[こくれんしょくりょうのうぎょうきかん]:FAOなど)では、「フードロス・アンド・ウェイスト(Food Loss and Waste)」として、以下の二つを区別することがあります。
- フードロス (Food Loss): 生産(畑)から加工、流通(卸売)の過程で失われる食品。 (例:収穫時に販売できないと判断されたものや採り残し、輸送中にキズがついてしまったものなど)
- フードウェイスト (Food Waste): 小売店や飲食店、家庭での消費の過程で捨てられる食品。 (例:売れ残り、食べ残し)
この定義でいうと、日本の「食品ロス」は、主に「フードウェイスト」に近い意味となります。
なぜ混同される? 日本での使われ方
日本では、これらを区別せず、「フードロス」という言葉が「食品ロス(=食べられるのに捨てられる食品)」と同じ意味にとらえられることも多く、テレビやネットなどのメディアや日常会話の中でもお店の売れ残りや家庭での廃棄を指して「フードロス」と呼ばれることがあります。
厳密には「食品ロス」と「フードロス」はどの過程で捨てられたものなのかという部分での違いはありますが、どちらの言葉を使うにせよ、指し示している社会的な課題は「食べられる貴重な食べ物を、無駄にしてはいけない」という点で共通しています。
タベスケのミッション
フードシェアリングサービス「タベスケ」のサービスは、これらの言葉の定義をふまえた上で、日本の「食品ロス(フードウェイスト)」、特にお店で発生する、食べられるのに捨てられる食品の削減をミッションとしています。
タベスケは、自治体が主導となって地域の店舗さん(パン屋さん、お弁当屋さん、八百屋さんなど)と市民の皆さんをアプリを通して、マッチングすることで、廃棄されそうになっていた美味しい食品を「お得に」「楽しく」救い出すお手伝いをしています。
またこのタベスケのサイトでは、食品ロスに関する豆知識や食品の保存方法などのコンテンツを通して、サイトを訪れてくださる皆様と一緒に家庭から出る食品ロスの削減に取り組んでいければと考えています。
言葉の違いを超えて、行動へ
「食品ロス」と「フードロス」。言葉を深掘りしていくと、ちょっとした違いはありますが、どちらも私たちが向き合うべき大切な課題です。今回はこの二つの言葉の違いについてお伝えしましたが、最も重要なのは「もったいない」を減らすための具体的な行動です。
あなたの身近な場所から少しずつ「食品ロス(フードロス)削減」のアクションを始めましょう!