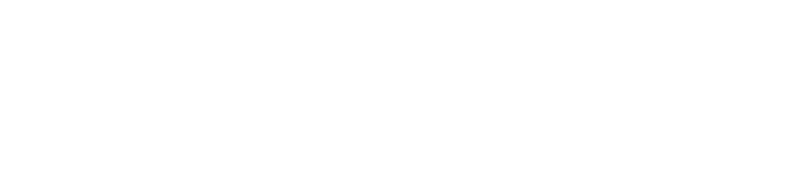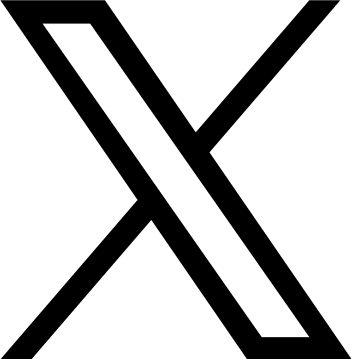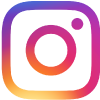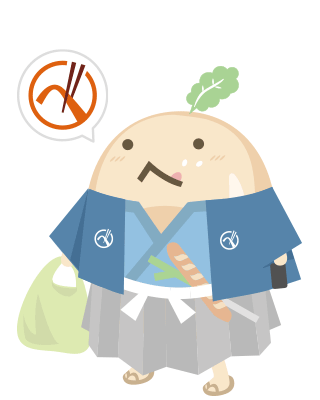食品ロスとは
食品ロスとは、「まだ食べられるのに捨てられてしまう食品」のことです。例えば、賞味期限が切れた食品、作りすぎた料理、形が崩れてしまった規格外の野菜や果物、そして日々の食事での食べ残しなどがこれにあたり、食品ロスの問題は世界中で深刻な社会問題となっています。
食品ロス削減に向けた日本の法律と取り組み
日本では、2019年10月1日に「食品ロスの削減の推進に関する法律」、通称「食品ロス削減推進法」が施行されました。この法律は、国や地方自治体が食品ロスに対する基本方針を策定し、具体的な施策を推進するための基盤を定めています。
また、食品関連事業者向けには、さらに以前から「食品リサイクル法」が2001年より施行されています。この法律は、食品の製造・加工時に発生する食品廃棄物や、売れ残り、食べ残しといった食品の減量・発生抑制を促し、発生してしまったものについては飼料や肥料として有効活用(リサイクル)する取り組みを推進するものです。
依然として残る課題と私たちにできること
これらの法律や取り組みにもかかわらず、食品ロスは依然として大きな課題です。環境省と農林水産省が発表した令和5年度(2023年度)の推計によると、日本の食品ロス量は年間約464万トンで国連世界食糧計画(WFP)による食料支援量370万トン(2023年実績)の約1.3倍。国民一人当たりに換算すると、約37kg、毎日おにぎり1個分の食品を捨てていることになります。このうち家庭系の食品ロスが約233万トン、事業系の食品ロスが約231万トンとなっています。
家庭系の食品ロスとは、各家庭での食べ残しや、賞味期限切れなどで手つかずのまま捨てられる食品です。一方、事業系の食品ロスは、食品メーカーでの製造過程における規格外品や、飲食店での食べ残し、スーパーマーケットでの売れ残りなどが含まれます。
食品ロスは世界的に見ても大きな社会問題であり、同時に私たちの身近な生活の中で発生しています。この大きな問題を解決へと導くためには、法律や事業者の努力だけでなく、私たち一人ひとりが食品ロスに対して意識と関心を持ち、削減に取り組んでいくことが不可欠です。
「まだ食べられるのに捨てられる」という悲しい食品ロスを減らすための一つの手段として、食品ロス削減を支援するマッチングサービス「タベスケ」を皆さんの日々の生活に取り入れてみてください。その小さな一歩が、食品ロスゼロへの大きな変化につながるはずです。